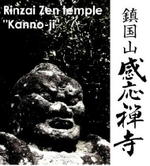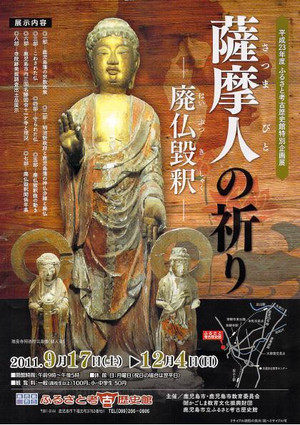六月燈 満員御礼
7/17の夜は感應寺恒例の六月燈が行われました。
雲山和尚頂相の展示について
鹿児島も秋の気配が高まっています。
感応寺もお彼岸を過ぎ、穏やかな境内の様子です。
さて、鹿児島市立ふるさと考古歴史館にて特別企画展
「薩摩人の祈り -廃仏毀釈- 」が開催されています。
12月4日まで(月曜休館)です。
当山からも県有形文化財の雲山和尚頂相を特別に
貸出し、展示して頂くことになりました。
雲山和尚は島津貞久公の命を受け感應寺の復興
に当たった中興開山で、讃文中には足利尊氏公
が雲山和尚を称えた和歌も書かれています。
十代徹堂和尚の時代に作られ、県内最古の頂相
(禅僧の肖像画)です。
毎年4月8日の花まつりのみの展示でしたので、
法縁かなって皆様にごらんいただければと思います。
会場のふるさと考古歴史館は鹿児島市の谷山地区
慈眼寺(ここも廃仏毀釈で廃寺になりました)公園
内にあります。
http://www.k-kb.or.jp/koukokan/
はなまつりのご案内と義援金のお願い
大変ご無沙汰しておりました。
振り返ってみると、昨年8月から半年以上、更新せず・・・
新年度になりましたので、心機一転ブログを更新して
行こうと思っております。ご容赦下さい。
さて、明日4/8は感応寺の恒例行事 はなまつりです。
例年のごとくですが、境内本堂の前に花見堂を設けています
ので、甘茶をかけてお釈迦様のお誕生日をお祝いして
下さいますよう、お願いいたします。
また、東日本大震災の被害に遭われた方々に対して、
心よりお悔やみ申し上げます。また、避難されている方々
に対しても、十分にご自愛いただければと思います。
感応寺でも、地震翌日より、賽銭箱の浄財をすべて義援金に
させていただいております。当分の間の予定ですが、集められた
義援金は日本赤十字社鹿児島県支部へ送る予定です。
お寺にお越しの際は、ご協力をお願い致します。
また、野田郷としては以前から交流のある岩手県野田村への
支援について検討が進められているようです。
微力ながら感応寺もご協力をさせていただく予定です。
写真は、送っていただいた野田村の様子です。
子安地蔵例大祭が開催されました。
11月23日は境内にあります子安地蔵の例大祭が開催されました。
100円ずつ3万人の浄財をいただいて建立された子安地蔵も
昭和58年以来毎年この11月23日が縁日になっています。
そのとき記念法要の導師を務めていただいた松原泰道和尚様も
今年天寿を全うされて、またこの例大祭も感慨があります。
本年は引き続き、鹿児島大学名誉教授の石澤隆先生による
「医者は患者さんに助けられる」というタイトルの講演がありました。
石澤先生は旧野田町出身、御父様の石澤茂徳先生とともに、
感應寺に縁が深い方でいらっしゃいます。
当日は長い外科医としての生活や、専門であられる大腸肛門に関する
治療経験をふまえて、患者さんと医者との立場を越えた関わり、
患者としての心構えについてお話をされました。
スライドでは、リアルな映像が流れてちょっとグロテスクなものが苦手な
不肖にとっては見たいような、見たくないような時間でしたが、
本堂には入りきれないぐらいの方々が熱心にお話を聞かれていました。
仏前結婚式
本日は、本堂にて仏前結婚式が執り行われました。
教会や神社での結婚式は多くみられますが、
禅宗のお寺での結婚式も最近静かなブームになっているようです。
とは言いつつ、やはり1年に1度あるかないかという割合ですが。
仏前に結婚を報告する形の式では、読経があったり、
新郎新婦の誓いの言葉があったり、三三九度があったりと、
(本日は略式で皆さんで茶礼をしました)
何となく、皆さんがイメージできるものかもしれません。
ただし、指輪の交換の代わりに基本的に「お寿珠」の交換が
あるところが仏前のちょっと目新しい所かもしれませんね。
披露宴や仲間内のパーティなど、結婚式のスタイルが「楽しむ」こと
に主眼がおかれるようになっている昨今、シンプルに「誓う」ことを
先祖に感謝しつつ執り行う仏前結婚式の形が、逆に新鮮に映る
時代になってきているのが実情です。
お寺がそのような「誓い」の支えになりうる場所であるために、
できることは何なのか?
そんなことを考えた秋の日でした。
本日ご成婚のお二人、ご結婚おめでとうございます。
六月燈 野田郷島津太鼓・島津義秀さんのお話
約半年振りの更新になりました。
7月17日は六月燈が執り行われました。
鹿児島では、夏祭りとして知られるこの行事ですが、元々は
当寺に墓所がございます、島津家初代忠久公の命日、旧暦の
6月18日に合わせ、家臣が灯籠をともし、それが庶民に広まった
という説もあるといわれており、感応寺にとっても非常に意味の
ある行事の一つです。
当日はあいにくの大雨で野外での奉納行事や出店も中止に
なり、ひっそりとした中にも多くの方がこの年中行事にご参加
されました。ありがとうございました。
毎年島津家墓所 五廟社にて奉納演奏をしていただく、野田郷
島津太鼓の皆さんも、雨のため本堂前にての演奏となりましたが、
篤姫をテーマにした新曲「北へ」を披露していただきました。
法要の後に、加治木島津家当主 島津義秀さんによる講演
薩摩琵琶の演奏とそれにまつわるさまざまな歴史の裏話、
そして最近熱心に活動されている郷中教育に関するNPOのこと
など、あっという間の時間をすごさせていただきました。
薩摩琵琶は島津日新公の命で盲僧が始めた歴史があり、
聴衆の皆様も、熱心に耳を傾けていらっしゃいました。
六月燈が終わると、境内もせみの鳴き声がやかましくなります。
せみよりもやかましい世の中ですが、皆様十分に暑中お見舞い下さい。
新年のご案内
大変遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。
本年も、感應寺に関係する方々のご多幸をお祈りしております。
さて、感應寺から幾つかご案内がございます。
(1)1/18(金) 初観音法話会が開催されます。
日時 一月十八日(金)昼二時より(昼のみ)
教師 佐賀県 正法寺住職 矢岡 正道 師
演題 「あたり前のこと 思いやりの心」
皆様お誘いあわせの上お越しください。
(2) 二月三日(日)午後二時より節分星祭り、大般若祈祷法要を
謹修致しますので、お誘い合わせお参り下さいます様御案内致します。
特別の厄払い希望の方は、別の紙に名前、性別、年齢(数え年)を
お書きの上、年齢に一つ加えた数の供物(餅・菓子等)を添えて
前日までに申し込んで下さい。
本年の厄年は以下の通りです。
男性 二十五歳(昭和五十九年生) 四十二歳(昭和四十二年生)
女性 十九歳(平成二年生) 三十三歳(昭和五十一年生)
(3)大河ドラマ篤姫の中で、感應寺が(ほんの少しですが)紹介されます。
1/20(日)の放送分です。(ドラマ終了後歴史解説のコーナーにて)
ご覧になってください。
御詠歌の講習会
6月3日は御詠歌会員の皆様が集まって、佐賀より講師の先生をお招きしての
特別講習会がひらかれました。7月の九州大会にそなえて「恩師追悼御和讃」
をみっちりとお稽古されました。
今年はいちき串木野市の良福寺さんの会員の方々と合同で披露いたします。
両寺合わせると40人近くの方が一同に御詠歌をおとなえするご様子は壮観で
もあり、またなんとも厳かな心安らかなひと時になります。
 御詠歌は拍子・鈴鉦を用いて、仏様祖師様を讃仰し、また
御詠歌は拍子・鈴鉦を用いて、仏様祖師様を讃仰し、また
信仰の心をお唱えするものです。とはいっても、堅苦しい
ものではなく、また歌の上手下手も関係ありません。
感應寺では毎月3・23日の2回昼夜行っていますので、興味の
ある方はご連絡いただければ詳しい説明を致します。